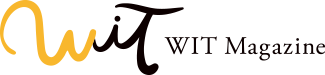テレビのようなマスに訴えかけるコンテンツから、特定の人たちで交流する「コミュニティ」に時間を使う人が増えている。コミュニティは、ビジネスとしても注目されるようになってきた。ファンコミュニティ用のプラットフォームを開発・運営しているオシロ株式会社の代表取締役社長 杉山博一さんに、ファンコミュニティについて伺っていく。
ファンコミュニティとは?

私はいくつかの会費制コミュニティに入っていますが、そのカラーはさまざまです。杉山さんが考える、ファンコミュニティとはどんなものですか?

ファンコミュニティとは「あるコンテンツや価値観に共感している熱心な人たちの集まり」だと思っています。さらに、共通な価値観を持った人が集まる「居場所」にもなっています。

「居場所」という言葉は、最近よく耳にしますね。

ところが、実は最近注目されたわけではなく、1991年に米国で出版された『The Great Good Place』という本に「サードプレイス」という単語が出てきているんです。地域とのつながりや、カフェ、バー、集会所、教会といった、サードプレイスが少なくなってきたことに、危機感を覚えて研究した学者がいたんですね。

「居場所」は「サードプレイス」と考えればいいんですね。

そうですね。その本が出る10年ほど前から論文などには出てきているので、そこまで遡ると、40年ほど前から出てきた考え方です。

そんなに古い考え方なんですね。一方で、今のようにオンラインでつながる「コミュニティ」が増え始めたのは最近ではないでしょうか。

ビジネスの人たちが注目し始めたのは最近と言えます。Facebookが2017年にミッションを変更し、「コミュニティづくりを応援し、人と人がより身近になる世界を実現します。」となりました。Facebookが、人と人を繋ぐことから、コミュニティづくりを応援することを主軸とすることで、世界的に注目されることになったんです。
ファンが集まるための「旗」とは?

ファンコミュニティを始めようと思ったとき、必要なものは何ですか。

まずは、ファンが集まる「旗」が必要。いいかえれば、オーナーが掲げるコミュニティの軸のようなものです。人のより所として独特の世界観や価値観、テーマを持っていなくてはなりません。テーマに「偏愛性」があるほどいいと僕は思っているんです。なによりオーナー自身がそのテーマに熱量を持って活動していることが大切です。

「偏愛」、いいですね。杉山さんが考える偏愛とはどんなものですか。

多くの人にとってなんてことのない、偏ったものに対する愛でしょうか。一般的に誰もがいいと言うものではなく、いびつなものだったり、ニッチなものだったりします。

ニッチなものがいいんですね。

例えば、「野球」はメジャーなスポーツで、決してニッチではない。ところが「野球を文章で表現する」という行為を掛け算して「野球×表現」となると、偏愛の要素が一気に強まると思っています。例えば、「文春野球学校」は野球好きなだけでなく表現をしたい人が集まっているコミュニティで、そこには狭く深い「偏愛」があるんですよね。

狭くなると「偏愛」感が増しますね。偏愛があるとなぜいいのですか?

ニッチで見つけにくいテーマであるほど、コミュニティのつながりが強くなります。逆にどこにでも転がっているようなテーマの場合、あえてコミュニティに入らなくても出会えるので、コミュニティの価値は高まりません。偏愛に熱量が加わると、狭く深いものが生まれます。絆が強くなり、壊れにくく、そして続きやすいのです。

偏愛でつながっていて、他に見つけることができない場所なら、ずっと続けたいでしょうね。

そうなんです。加えて、スタート時には、その旗に人が集まるかどうかが大切です。熱量の高いフォロワー数だったり、独自のネットワークだったり。立ち上げる前にそういったつながりがあるといいですね。
成功しているコミュニティの例は?

うまくっているコミュニティの例があれば教えていただけますか?

米国の話になりますが、コミュニティとの相乗効果で事業が伸びた例があります。オンラインコミュニティとシェアオフィスの事業を掛け合わせたものです。月額制で、オンライン上で交流できる場所があり、さらにシェアオフィスを1日使える権利が付いてきます。

どんなところが魅力だったのでしょうか?

シェアオフィスを使うのはフリーランスの方が多いんです。まずオンラインコミュニティが、孤独なフリーランスの居場所になっていった。そこから、コミュニティ内にいるスキルの高い人たち同士で「プレゼン資料にアドバイスが欲しい」といった相互補助のコミュニケーションが生まれ、助け合って仕事もうまくいくようになっていったんです。スキルが高い人の集まりですから、自然とうまくいきますよね。

上手く回っていくと、会員の人にとってはいいことしかないですね。

さらに、フリーランスの人たちの事業がうまくいくと、1日使える権利だけでは不便を感じるようになり、月額でオフィスを借りたくなるんですね。そこで、メイン事業としていたシェアオフィスを借りる人が増えて、会社が潤っていく仕組み。コミュニティをスタートとして、シェアオフィス事業が何倍にも伸びていきました。

企業にとっても、会員にとっても、コミュニティが大きな価値になった例ですね!
広く浅くではなく、「偏愛」を旗印に人を引き寄せる「ファンコミュニティ」。集まった人同士でシナジーが生まれ、事業が活性化していくこともある。次回は、ファンコミュニティを成功させるための秘訣を伺う。

杉山博一さん
元アーティスト&デザイナー。世界一周後、アーティスト活動開始、30才を機に終止符。ニュージーランドと東京の二拠点居住&外資系IT企業代表を経て、現在は、東京に定住し「日本を芸術文化大国にする」という志を持ち、「OSIRO」を開発。システムだけでなく、サポートも合わせて行い、2020年東洋経済誌「すごいベンチャー100」に選出される。https://osiro.it
栃尾江美
ストーリーと描写で想いを届ける「ストーリーエディター」。ライターとして雑誌やWeb、書籍、広告等で執筆。数年前より並行してポッドキャスターも